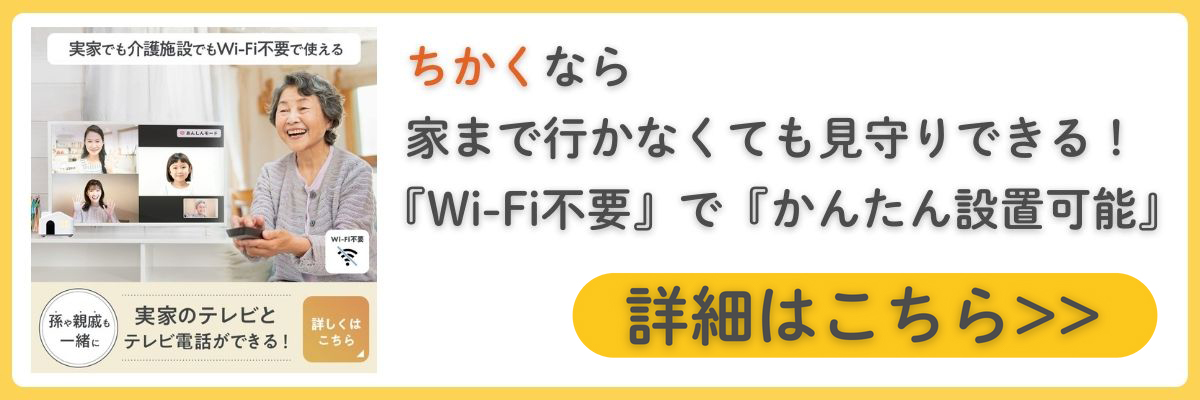一人暮らしの高齢者を守る対策とは?リスクや将来的な備えも解説
コラム
高齢化が進む現代の日本では、一人暮らしをする高齢者の数が年々増加傾向にあります。こうしたなかで、高齢者は体調の急変や転倒、詐欺被害など、さまざまな危険に直面するリスクも高まっており、注意が必要です。
特に、身近に頼れる人がいない場合には異変に気づくのが遅れ、大事に至るケースも少なくありません。これらのリスクを未然に防ぐには、行政サービスや民間支援、デジタル技術の活用といった多様な対策を組み合わせることが大切です。
本記事では、一人暮らしの高齢者があんしんして暮らし続けるために押さえておきたい具体的な備えについて解説します。
一人暮らしの高齢者のあんしんを守る対策

一人暮らしの高齢者が安全かつ快適に暮らし続けるためには、本人や家族が公的・民間の見守り対策を把握しておくことが大切です。
近年では、安否確認や訪問支援など、自治体の支援による見守り活動が広がっています。また、民間の生活支援サービスでは、家事や買い物などのサポートにより、日常生活での負担軽減が可能です。これらに、デジタル機器を活用した見守りサービスを組み合わせれば、よりあんしんして見守りができる仕組みを構築しやすくなります。高齢者本人にとっても、万が一に備えておくことは、精神的なあんしん感につながるでしょう。
ここでは、一人暮らしの高齢者のあんしんを守るための具体的な見守り対策を紹介します。
行政サービスを利用する
多くの自治体では、高齢者に対する定期的な安否確認や訪問支援を行う「見守り活動」を実施しています。このような地域による支援制度は、日常の小さな変化にも気づいてもらえるあんしん感があり、一人暮らしの高齢者にとっても心強い取組みです。また、地域の集会所やサロンなどで行われる交流活動への参加では、他者や社会との接点が生まれるため、孤立の防止や心身の機能維持にも役立ちます。
しかし、支援の受け方や交流活動への参加方法がわからず、戸惑ってしまう高齢者の方も少なくありません。まずは、居住地域で実施されている支援や交流活動を家族で一緒に調べてみるとよいでしょう。興味の持てそうな活動があれば、家族が参加のきっかけづくりをサポートすることも大切です。
民間の生活支援サービスを活用する
民間の生活支援サービスの活用も、一人暮らしの高齢者にとって助けとなります。たとえば、配食サービスや買い物代行は、栄養バランスの維持や外出負担の軽減につながる実用的なサポートの一つです。
また、重い荷物の運搬や高所作業なども、代行サービスの活用により安全に対応してもらえます。最近では、掃除や洗濯、通院の付き添いなど、支援内容が豊富です。民間が運営する支援サービスは、生活スタイルや希望に合わせて柔軟に選べる点も大きな魅力といえるでしょう。
自宅近隣で利用できるサービスの情報は、地域のケアマネジャーや包括支援センターに相談すると提供してもらえます。家族が情報収集を手伝いながら、本人の希望や生活状況に応じて支援内容を選ぶとよいでしょう。
見守りカメラなどのデジタル技術を使用する
デジタル技術の活用も、高齢者の一人暮らしに起こり得るリスク対策の一つです。特に見守りカメラは、離れた場所からスマートフォンやパソコンを通じて安否を確認できるため、離れて暮らす家族におすすめです。人感センサーやドア開閉センサー付きの製品であれば、生活パターンの変化や異常をいち早く察知するのに役立ちます。
行政や民間の支援サービスに加えて、こうしたデジタル技術を取り入れれば見守り体制をより強化でき、高齢者本人も家族もあんしんして過ごせるようになるでしょう。
なお、見守りカメラについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
内部リンク:見守りカメラのメリットや注意点は?選ぶ際のポイントも解説
将来を見据えて検討しておきたい支援と備え

年齢を重ねると、心身の状態が変化することがあります。いざというときに慌てないためにも、早い段階から住まいの選択肢や要介護高齢者に対する支援を把握し、検討しておきましょう。
たとえば、サービス付き高齢者住宅では、安否確認や生活相談サービスなどを受けながら生活ができます。また、要介護認定を受けた場合は介護保険制度を通じて、訪問介護やデイサービス、住居改修などの支援を受けることが可能です。専門職員の計画的な支援によって、自立した暮らしを継続しやすくなるでしょう。ここでは、将来を見据えた具体的な支援と備えを解説します。
サービス付き高齢者向け住宅を検討する
サービス付き高齢者向け住宅は、施設スタッフによる状況確認や生活相談サービスを提供する賃貸型の住まいです。定期的な安否確認により、急な体調の変化にも対応しやすい環境になっています。室内はバリアフリーに対応しており、転倒防止や移動のしやすさといった安全面にも配慮されており、自宅のような自由度を保ちつつ、必要な支援だけを受けられる点も魅力です。

引用:厚生労働省「地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて」

引用:厚生労働省「地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて」
厚生労働省によると、サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数は平成24年の段階で2,245戸でしたが、令和4年では8,130戸と大きく増加しています。利用者数も同様に増加傾向にある現状からも、高齢者にとってあんしんして暮らせる選択肢であると同時に、家族の負担を和らげる有効な手段として注目されています。
公的介護保険を利用する
公的介護保険制度は、要支援・要介護と認定された40歳以上の方が、自己負担を抑えて必要なサポートを受けられるよう、介護にかかる費用の一部を補助する仕組みです。たとえば、訪問介護やデイサービスのほか、手すりの設置や段差解消といった住宅改修、福祉用具のレンタルにも活用できます。
公的介護保険を利用する場合、利用者の状態や生活環境に応じて、専門職員が介護サービス計画を作成してくれます。専門的な視点でサポートしてもらえるため、介護の知識が少ないご家族でもあんしんして利用ができます。
介護サービスの利用の流れは、以下をご参照ください。
出典:厚生労働省「介護保険制度について」
高齢者の一人暮らしが年々増加している背景


引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
内閣府発表の「令和7年版 高齢社会白書」によると、65歳以上の人口は総人口の29.3%を占めており、日本では急速に高齢化が進んでいます。さらに、総人口の減少にともなって高齢化率は年々上昇しており、今後もこの傾向が続くと見込まれています。

引用:内閣府「令和7年版 高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
また、一人で暮らしている高齢者も増加傾向にあり、2020年の段階では22.1%でしたが、2025年には25.4%に達する見込みです。これらを踏まえ、一人暮らしの高齢者が年々増加している背景について解説します。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
生活の利便性が向上している
近年はデジタル化の進展により、暮らしの利便性が大きく向上しています。総務省が実施した「令和6年通信利用動向調査」では、70~79歳のインターネット利用率が69.8%に達し、前年度(67.0%)から微増しました。さらに、80歳以上でもインターネットを利用している人が3割を超えています。
また、ネットスーパーや宅配食などのサービスが普及し、外出せずに買い物や食事の準備を済ませられる環境が整ってきた点も、高齢者の一人暮らしが増えた背景の一つです。こうしたサービスの広がりは、高齢者が一人でも快適に暮らせる環境づくりを後押ししています。
経済的に自立している
内閣府が実施した「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、経済的な暮らし向きについて「心配なく暮らしている」と回答した高齢者は、全体の65.9%にのぼりました。さらに、65歳以上のうち36.5%が「仕事による収入を得ている」と答えており、就労を通じて経済的に自立している高齢者も一定数いることがわかります。
また、高年齢者雇用安定法改正により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となりました。こうした制度の整備も、一人暮らしの高齢者を経済的に支える要因の一つといえます。
出典:内閣府「令和6年度 高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)の結果(概要版)経済的な暮らし向きについて」
出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
未婚の割合が増加している
高齢者の一人暮らしが増加している背景には、未婚率の上昇も影響しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2020年時点で65歳以上の単身者のうち、未婚の男性は33.7%、女性は11.9%でした。2050年には男性が59.7%、女性が30.2%に達すると見込まれており、単身で暮らす高齢者の増加が予想されています。
加えて、お子さまがいない、あるいは親族が遠方に暮らしているなど、身近に頼れる存在がいない高齢者も少なくありません。その結果、やむを得ず一人暮らしを選択するケースも見られます。こうした状況からも、家族構成の変化や人間関係の希薄化が、高齢期の暮らし方に影響しているといえるでしょう。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)」
内部リンク:高齢者の一人暮らしの現状は?起こり得る問題と安心のための対策
高齢者が一人暮らしを続けるリスク

高齢者の一人暮らしでは、転倒や急病などのトラブルが起きた場合に、すぐに助けを呼べず、発見が遅れてしまうことがあります。また、人とのかかわりの減少がきっかけで孤立化し、心身の機能が低下しやすくなったり、買い物や調理が負担に感じ、食事の偏りから栄養不足に陥り、体力や免疫力の低下を招くリスクもあります。加えて、高齢者を狙った犯罪に巻き込まれるケースも後を絶ちません。
ここでは、高齢者の一人暮らしで起こり得るリスクと対策を具体的に4つ解説します。
ケガや急病の際に対応が遅れる
一人暮らしの高齢者にとって、転倒や急な発作などが起きた際、すぐに助けを呼べない状況は深刻です。体を動かせない状態では自力で通報することが難しく、発見の遅れが症状の悪化や回復の遅れにつながるおそれがあります。
特に、骨折や頭部を強く打つなどの大きなケガは、要介護状態につながるケースも少なくありません。こうした緊急時にできるだけ迅速に対応するためにも、見守りサービスの導入や定期的な安否確認の手段を確保しておくことが大切です。
心身の機能が低下して日常生活に支障が出る
一人暮らしの高齢者が社会との接点を失うと、心身の機能が低下するリスクが高まります。周囲とのかかわりが少ない生活が続くと、寂しさや不安を感じやすくなり、孤立化していきます。また、外出量が減り、体力や筋力の低下にもつながります。
こうした心身の衰えが進むと、買い物・通院・掃除といった日常の動作にも支障をきたす可能性もあり、実際のデータでは、運動をよく行っている者は、糖尿病、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率が低いとされています。つまり、適度な運動は健康維持において重要な役割を果たします。
心身ともに健康を保つためにも、ゲートボールやハイキングなどの運動、地域とのかかわりを持ち続けることが大切です。
料理が負担になり栄養が偏る可能性がある
一人暮らしの高齢者のなかには、買い物や調理を負担に感じる人も少なくありません。その結果、手軽に食べられる菓子パンやレトルト食品に頼りがちになり、栄養が偏ることで健康リスクが生じます。
さらに、活動量の低下により食欲が落ち、食事量が極端に減る点も問題です。厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、低栄養傾向(BMI≦20kg/m2)にある人の割合は以下のようになっており、年齢が上がるほど低栄養になりやすいことがわかります。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 65~69歳 | 9.7% | 19.0% |
| 70~74歳 | 12.7% | 19.0% |
| 75~79歳 | 12.7% | 23.1% |
| 80~84歳 | 15.3% | 19.9% |
| 85歳以上 | 17.2% | 27.9% |
低栄養状態が続くと免疫力や筋力の低下を招き、感染症や転倒のリスクが高まります。健康的な生活を送るためには、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
詐欺や窃盗などの犯罪に巻き込まれるおそれがある
高齢者を狙った犯罪は年々巧妙化しており、特にオレオレ詐欺や預貯金詐欺などの特殊詐欺による被害は後を絶ちません。警察庁の統計では、2024年に特殊詐欺の被害に遭った人のうち、高齢者層が65.4%を占めており、社会問題となっています。
また、点検業者を装った窃盗や悪質な訪問販売など、日常生活のなかで思いがけず犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。こうした被害を未然に防ぐには、外部に通報できる緊急ブザーやモニター付きインターホンの設置、留守番電話の活用が大切です。ほかにも、高齢者の不安や悩みをすぐに相談できる環境づくりが重要です。
出典:警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版) 」
まとめ

一人暮らしの高齢者は今後さらに増加が見込まれ、万が一に備えた早めの対策が欠かせません。近年は、行政や民間による見守りサービスや家事代行などのサポートも充実しており、これらを状況に応じて組み合わせることが大切です。また、デジタル技術を取り入れた一人暮らしの高齢者の見守り対策も有効です。
見守りサービス「ちかく」は、テレビ電話で一人暮らしの高齢者の顔を見ながらやりとりができるほか、「あんしんモード」の活用により、起床や在室状況の確認もかんたんな操作で行えます。
また、招待機能を使えば、家族みんなで見守りに参加できる点も魅力であり、ケガや急病による発見の遅れや犯罪のリスクから守る備えとなります。
詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。
ちかく|見守りよりも、やさしい選択