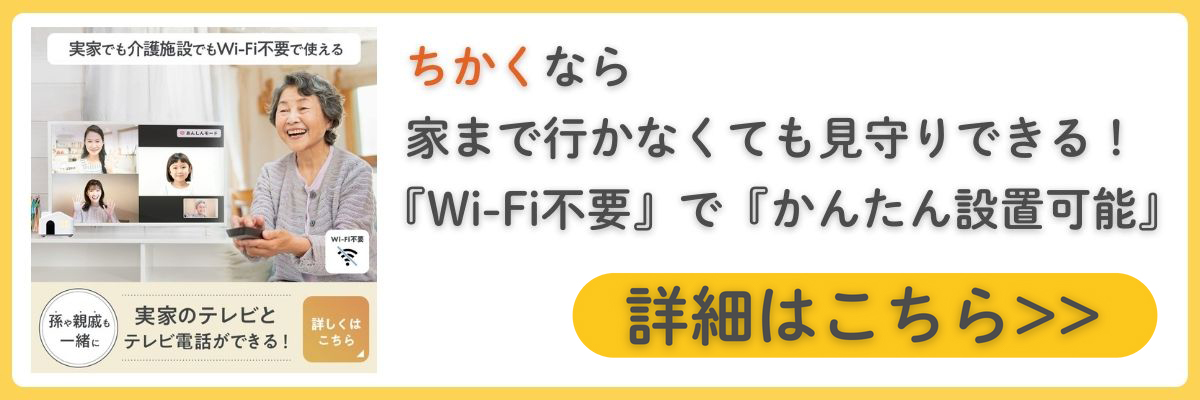高齢者の一人暮らしの生活費はいくら?支出を抑えて老後に備える方法
コラム
高齢の方が一人暮らしを続ける場合、夫婦二人暮らしと比べて一人あたりの生活費負担は大きくなる傾向があります。「年金収入だけで足りるのか」「子が経済的にサポートすべきか」と不安を抱く方も多いでしょう。さらに、将来的な医療費や介護費などの支出も見込んでおく必要があります。こうした金銭面の全体像を把握しておくことは、親があんしんして一人暮らしを続けるために欠かせない要素です。
本記事では、一人暮らしの高齢者に必要な生活費やその内訳、支出を抑えて老後に備える工夫をわかりやすく解説します。
一人暮らしの高齢者人口は年々増加傾向にある

内閣府によると、令和6(2024)年10月1日時点の日本の総人口は1億2,380万人でした。このうち65歳以上の高齢者人口は3,624万人に達し、総人口の29.3%を占めて過去最高を更新しています。
特に、一人暮らしの高齢者は年々増加傾向にあり、2020年時点では女性が22.1%、男性が15.0%でした。1980年には女性11.2%、男性4.3%にとどまっていたことを踏まえると、約40年間で大きく伸びている状況です。
高齢化は今後も進行すると見込まれ、2050年には高齢者が総人口の37.1%を占めると予測されています。これに伴い、一人暮らしの高齢者数もさらに増える見通しで、その推定割合は女性が29.3%、男性が26.1%に達します。こうした人口構造の変化は、高齢者の生活支援や安全対策の重要性をいっそう高める要因といえるでしょう。
関連記事:高齢者の一人暮らしの現状は?起こり得る問題と安心のための対策
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書」
高齢者の一人暮らしにかかる生活費

65歳以上の無職高齢者が一人暮らしをする場合、1か月あたりの平均消費支出は平均15万4,601円です。これは夫婦二人世帯の一人あたりの生活費よりも多く、すべての生活費を一人で負担することによる支出の増加と考えられます。
また、若年層と比べると、住居費や交通・通信費は少ない一方で、光熱・水道費や保健医療費は多い傾向にある点も特徴です。こうした比較から、高齢者は自宅で過ごす時間が長く、健康管理や日常の快適性に関する支出の比重が大きい状況がわかります。限られた収入のなかでやりくりするためには、支出項目ごとの特徴を把握し、優先度を意識した家計管理が重要です。
出典:総務省統計局「家計調査 2024年(令和6年)平均 (2025年2月7日公表)」
平均消費支出
総務省統計局の「1世帯当たり1か月間の収入と支出(男女・年齢階級別)」によると、単身世帯全体の平均消費支出は月額16万9,547円でした。このうち65歳以上の無職は平均14万9,286円とやや低く、35~59歳の無職および勤労者の平均18万4,750円と比べると約3万円少なくなっています。高齢者は年金を中心とした限られた収入で生活するケースが多いため、労働収入がある世代との差が数字に表れているでしょう。
また、総務省の「家計調査報告(家計収支編)」によれば、65歳以上の無職夫婦二人世帯の平均消費支出は25万6,521円で、一人あたりに換算すると約12万8,261円となります。一人暮らしの場合は生活費を分担できないため、一人あたりの負担が大きくなりやすいです。
出典:総務省統計局「家計調査 2024年(令和6年)平均 (2025年2月7日公表)」
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「家計調査 2024年 1世帯当たり1か月間の収入と支出(男女,年齢階級別)」
生活費の内訳と支出割合
| 項目 | 単身世帯(35~59歳) | 単身世帯(35~59歳) |
|---|---|---|
| 食料 | 47,673円 | 42,973円 |
| 住居 | 26,579円 | 13,677円 |
| 光熱・水道 | 12,585円 | 14,528円 |
| 家具・家事用品 | 5,309円 | 6,735円 |
| 被服及び履物 | 4,533円 | 3,656円 |
| 保健医療 | 6,815円 | 9,102円 |
| 交通・通信 | 27,755円 | 15,984円 |
| 教育 | 14円 | 12円 |
| 教育娯楽 | 21,021円 | 16,311円 |
| その他 | 32,465円 | 31,624円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「家計調査 2024年 1世帯当たり1か月間の収入と支出(男女,年齢階級別)」
上記の表は、単身世帯の生活費の内訳を年齢別で比較したものです。いずれの世代でも「食料」が最も大きな割合を占めていますが、65歳以上は35~59歳より約5,000円少なくなっています。これは、食事量の違いや、高齢者特有の節約志向が影響していると考えられます。
また「住居」や「交通・通信」は、65歳以上が35~59歳の約半分です。外出頻度の低さや、住宅ローンを完済している世帯が多いことが背景にあると推察されます。
一方で「光熱・水道」や「保健医療」は65歳以上の方が高めです。自宅で過ごす時間が長く、健康管理に関連する支出が増えることが要因といえるでしょう。
一人暮らしの高齢者の平均収入

総務省統計局が発表した「家計調査報告(家計収支編)」によると、無職で一人暮らしをする65歳以上の高齢者の平均収入は月額13万4,116円でした。そのうち、年金などの「社会保障給付」が12万1,629円と、全体の90.7%を占めています。支出が収入を上回るケースもあり、老後の生活に不安を抱く人は少なくありません。
一方、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」では、65~69歳の勤労者の年間平均給与は354万円で、月額に換算すると29万5,000円です。70歳以上の勤労者も月に約24万4,160円の給与を得ており、無職の場合と比べて収入が大きく増えるケースも見られます。
安定した老後を送るためには、年金だけでなく就業や副収入などを組み合わせた柔軟な収入設計が必要です。
出典:総務省統計局「家計調査 2024年(令和6年)平均 (2025年2月7日公表)」
出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
無理のない働き方で収入を増やすことも可能になっている
かつては60歳での定年が一般的でしたが、高年齢者雇用安定法の改正により、現在は70歳までの就業確保が努力義務となっています。
近年では定年制を廃止し、年齢を問わず働ける制度を導入する企業も増え、高齢者も体力や健康状態に応じた働き方を選べるようになりました。たとえば、在宅ワーク、シルバー人材センターを通じた地域での仕事です。
年金収入だけでは生活が不安な場合でも、就業により不足分を補えば、生活費のバランスが取りやすくなります。収入の補完は、生活費を過度に切り詰める必要性を減らし、精神的なゆとりにもつながるでしょう。さらに、働くことで生活リズムの維持や社会参加、孤立防止といった面でも大きな効果をもたらします。
出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
一人暮らしをする高齢者の生活費が不足しやすいポイント

年金だけで生活する一人暮らしの高齢者は、支出が収入を上回りやすく、生活費不足に悩むケースも少なくありません。
公的年金の受給額は現役時代の就労状況や加入年数によって差があり、十分な貯蓄がない場合は日々の支出管理が重要になります。内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」では、65歳以上の高齢者の55.5%が「貯蓄は足りない」と回答しました。
一方で、食費や光熱費、保険料、医療費などの生活に必要な支出は減らしづらく、無理な節約は健康や生活に支障をきたす恐れがあります。こうした不安を和らげるには、家族が出費の実態を理解し、本人の生活に寄り添ったサポートを行うことが重要です。
食費
食費は生活費のなかでも大きな割合を占める項目であり、近年の物価上昇により家計への負担が増しています。その影響で、食事回数を減らしたり、肉や魚などのタンパク源を控えたりする方も少なくありません。しかし、過度な節約は栄養不足を招き、体調不良や医療費増加の原因となることがあります。
内閣府の調査によると、「おいしいものを食べているとき」に生きがいを感じると答えた一人暮らしの高齢者は、51.6%に上りました。この結果からも、食事と心の健康が密接にかかわっていることがわかります。食費を削るのではなく、献立を事前に決めて買い過ぎを防ぐ、シニア割や特売日を活用するなど、無理のない範囲での節約が大切です。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
光熱費
光熱費は季節によって変動が大きく、特に夏場や冬場は冷暖房費がかさみがちです。高齢者は体温調節機能が低下しており、過度な節電は熱中症や低体温症などのリスクを高めます。安心して暮らしながら光熱費を抑えるには、日常のちょっとした工夫が大切です。
たとえば、断熱性の高いカーテンやマットを活用すると、光熱費の削減が期待できます。また、エアコンのフィルターを定期的に掃除すると冷暖房の効率が上がり、消費電力の抑制が可能です。ただし、一人暮らしの高齢者にとっては設置や掃除が負担になる場合もあるため、家族のサポートが欠かせません。遠方に住んでいる場合は、家事代行サービスや地域のシルバー人材センターを活用するのもよいでしょう。
保険料
高齢者にとって、保険は将来の医療や介護に備える重要な支出項目です。内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、65歳以上で生命保険に加入している人は54.4%となっています。また、病気やけがに備える保険に加入している人は全体の半数以上であり、65~69歳では63.4%と高い割合を占めています。
なお、必要性を十分に検討しないまま似た内容の保険を複数契約し、長期間にわたり不要な保険料を支払っているケースは少なくありません。そのため、定期的に保障内容を見直し、健康状態や生活に合った保険の整理が大切です。適切な判断を下すうえでは、家族のサポートが大きな助けとなります。
出典:内閣府「令和6年度 高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)の結果」
医療費
厚生労働省によれば、年齢が上がるほど医療費は増加する傾向にあることがわかっています。健康保険や高額療養費制度を活用しても、通院や薬代、検査費用などが積み重なると、年間を通じて大きな負担となりかねません。特に、慢性的な持病を抱える場合は、出費が継続する可能性があります。
加齢による心身の衰えは避けられず、医療費を完全に抑えるのは難しいです。そこで、定期検診を受け重症化を防ぎ、負担を軽減するための対策を行いましょう。また、高齢者の健康を維持するには、速やかに異変に気づける体制の整備も欠かせません。高齢の親と離れて暮らしている場合は、日常の様子を把握でき、異変時にはすぐに連絡や対応が可能な「見守りカメラ」の活用がおすすめです。
出典:厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度、医療保険制度分)」
あんしんな老後の暮らしを支える「見守り」という選択肢

厚生労働省によれば、生涯に必要な平均医療費は約2,800万円で、そのうち約6割(約1,604万円)は65歳以上が占めています。また、生命保険文化センターによると、住宅の改装や介護用ベッドの購入などに平均約47万円、月々の介護に平均約9万円かかるといったデータがあり、高齢者本人だけでなく家族にも経済的負担が見込まれます。加えて、親と離れて暮らす家族の場合、訪問に伴う交通費(新幹線や飛行機、ガソリン代、高速道路料金など)も発生します。
このように費用面での負担が大きいなか、一人暮らしの高齢者は体調不良や事故が起きた際に発見が遅れやすく、結果として医療費や介護費がさらに高額になる可能性があります。そのため、家族による見守りや支援がいっそう重要になります。
出典:厚生労働省「医療保険に関する基礎資料 ~令和3年度の医療費等の状況~」
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査(速報版)」
高齢者の「見守り」にはいくら費用がかかるの?
見守りサービスには、訪問型・カメラ型・緊急時通報型などの種類があり、費用はサービスの内容によって異なります。月額無料で利用できるものから1万円前後のものまで幅があるほか、初期設置費用がかかるケースも少なくありません。
たとえば、離れて暮らす親子がかんたんにつながれる見守りサービス「ちかく」は、月額1,980円(税込)で利用できます。主な特徴は以下のとおりです。
- 複数の親族が同時にサポートできる
- 一人暮らしの高齢者の急な体調変化や事故にも早期対応しやすい
このように、高齢者本人の安全確保だけでなく、遠方に暮らす家族の精神的負担の軽減にも役立つ、費用対効果の高い現実的な備えとしておすすめです。
関連記事:高齢者見守りサービスとは?6つの種類と選ぶポイントを解説
関連記事:見守りカメラのメリットや注意点は?選ぶ際のポイントも解説
関連記事:ちかく|見守りよりも、やさしい選択。
まとめ: 高齢者の一人暮らしを守るために、費用を見直してあんしんな環境を整えよう

高齢者の一人暮らしは、夫婦二人暮らしなどに比べて一人あたりの支出が多くなる傾向があります。年金収入だけでは生活費が不足するケースもあり、どの費用がどのくらいかかるのか、その内訳を理解したうえでの備えが大切です。
また、高齢者本人とその家族の経済的負担を軽減するためには、サポート体制を整えておきましょう。見守りサービスの活用は、一人暮らしの高齢者をサポートする選択肢の一つです。経済的な自立とあんしんできる環境づくりの両立が、高齢者の一人暮らしには欠かせません。
見守りサービス「ちかく」は、離れて暮らす親子が手軽につながれる仕組みを提供しています。費用を抑えながら高齢の親を見守りたい方は、ぜひこちらのページをご覧ください。
関連記事:ちかく|見守りよりも、やさしい選択。
※「ちかく」は株式会社チカクの登録商標です。