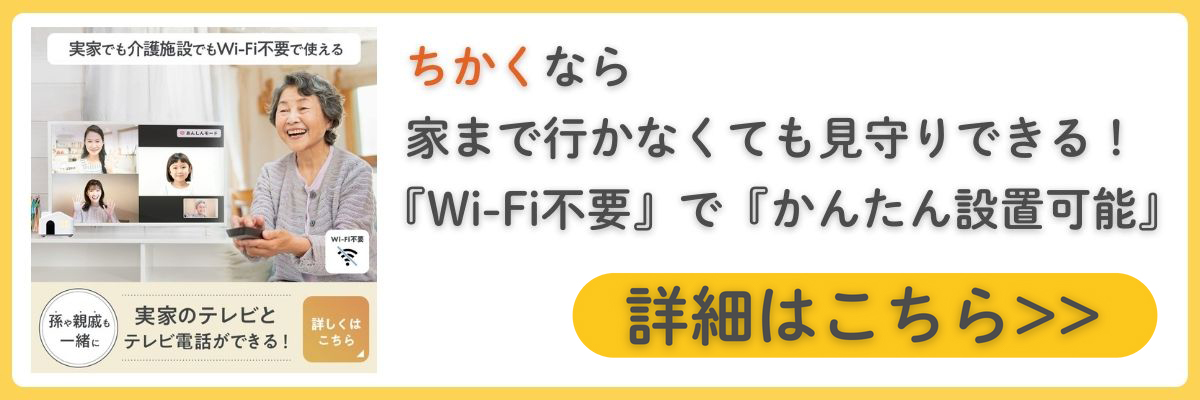【実態調査】遠距離介護「姿が見えない」に潜むリスクとは?帰省頻度や将来の備えについて
コラム
親と離れて暮らす方が抱える課題や不安について、40代〜50代を中心に男女300人を対象に実態調査を行いました。本記事では、調査結果から見えてきた遠距離介護のリアルな課題を解説するとともに、親子が安心して暮らすために「今からできる具体的な備え」を知りたい方へ向けて、具体的な解決策を提示します。
遠距離介護とは?データで見る物理的・心理的な距離

昨今、親と離れて暮らしているという人は珍しくなく、3組に1組以上の家庭が該当します。親の居住地との距離感について尋ねたところ、「同一市区町村」が約4割にのぼる一方、「別の都道府県(新幹線や飛行機の利用が必要な距離)」と回答した方が34%にのぼりました。
この物理的な距離は親子のコミュニケーションや、いざという時の対応にどう影響するのでしょうか。まずは、この「距離」というデータから想定される遠距離介護の具体的な課題や、親子の心理的な距離について解説していきます。
子の負担と親の遠慮の交錯によって帰省は一大イベント化
遠方で暮らす親に、どのくらいの頻度で会えているのでしょうか。距離のデータに面会頻度を掛け合わせると、帰省が「一大イベント化」している実態が見えてきます。

まず注目すべきは、親と会う頻度が「2〜3か月に1回」以下の層が合計で55.33%と、全体の半数を超える点です。特に「半年に1回」と「年1回以下」を合わせると40.00%にのぼり、多くの方が季節に一度も親と顔を合わせていない現状がうかがえます。
この背景には、子の物理的・金銭的な負担だけでなく、「子どもに迷惑をかけたくない」という親側の遠慮も存在すると推察されます。それを裏付けるのが、コミュニケーションの難しさとして18.3%の方が「親が本音を話してくれない」と回答している点です。
物理的な距離と、こうした親子双方の気遣いが、帰省を非日常のイベントにしてしまい、かえって日常の些細な変化や本音が見えにくくなるというジレンマを生んでいるのです。
遠距離で暮らしていることで不安も増大、モニタリングが重要に
子の不安を増大させる最大の要因は、親の生活が実質的に見えない「ブラックボックス化」です。今回の調査で、親と「別都道府県」に住み、かつ会う頻度が「季節に一回以下」で、さらに「特に生活支援をしていない」という最もリスクの高い状態にある人は、全体の17.7%(53人)にのぼることが分かりました。これは、約6人に1人の割合で、親がどのような生活を送り、どんな問題を抱えているか具体的に把握できていない可能性があることを示唆しています。

また、「急な体調変化や転倒」(44.7%)や「認知機能の低下」(29.7%)といった具体的な不安を抱えている方も少なくありません。「見えないこと」自体がリスクであると認識し、生活リズムから安否をそっと確認するような、プライバシーに配慮したカジュアルなモニタリングの重要性が高まっているともいえます。
「声は元気そう」本当の状況がわかるコミュニケーションとは?

親とのコミュニケーションの観点では、連絡頻度が月に数回以下に留まる家庭が多数派であり、さらにその手段が「声」だけの電話に偏っているため、親の本当の状況を把握できていないという二重の課題が見えてきます。今回の調査で、親と「週に1回以上」連絡を取る家庭は約36%に過ぎず、多くはそれ以下の頻度です。また、この限られたコミュニケーションの機会も、主な手段は電話やメッセージが中心となっています。

これらの手段では「親の状況が分かりにくい」と感じる人が多く、会う頻度の低さをコミュニケーションの質で補えていない実態があります。この「頻度の少なさ」と「質の低さ」は、親の変化を見過ごす大きなリスクとなっています。
ここからは、「量」と「質」のギャップに焦点を当て、親の状況理解につながるコミュニケーションのあり方について考えます。
手軽なコミュニケーションだけでは親の本当の状況がわかりにくい

親とのコミュニケーションには、子の約6割が何らかの難しさを感じており、特に「本当の体調や状況が分かりにくい」(31.3%)という課題が浮き彫りになりました。また、「親が本音を話してくれない」(18.3%)、「同じ話を何度も繰り返される」(17.0%)といった回答も多く、これらは認知機能の低下のサインを見逃すリスクや、親が隠しているSOSに気づけない可能性を示唆します。
この「分かりにくさ」は、子どもが抱く具体的な不安と直結したとき、より深刻な問題となります。離れて暮らす親の生活に対して不安に感じている割合が高い「急な体調変化や転倒」(44.7%)ですが、数カ月に一度の電話だけでこのリスクを察知するのは難しいでしょう。
また、LINEやショートメッセージ等でコミュニケーションを取っている方も少なくありませんが「孤独感や精神的な落ち込み」(14.0%)は、声のトーンや表情が読み取れないコミュニケーションだけでは見過ごされがちです。
このような課題を解決する鍵は、コミュニケーションの「質」を高める小さな工夫にあります。例えば、孫の写真を送るついでに「お母さんが撮った写真も送って」と気軽に頼んでみたり、日常の様子がわかる短い動画を送り合ったりするだけでも、得られる情報が増えるでしょう。さらに、室温や在室状況がわかるセンサーなどを活用すれば、熱中症や転倒事故などの直接的なリスクにも備えることができます。
「見えない」はリスク。遠距離介護のヒヤリ・ハット体験談

「見えない」状態をそのままにしておくことで、さまざまなリスクにつながります。
「離れて暮らす親に対してヒヤリとした体験」を聞いてみると、「父親が目の違和感を訴えるので病院に連れて行ったら、即日手術になった」「仕事中、実家の親が薬の副作用で数回倒れ、入院したと連絡があった」など、発見が遅れれば深刻な事態になりかねない事例が寄せられました。これらは、遠距離であるがゆえに日常の様子が見えず、変化のサインを見逃してしまった結果と考えることもできます。
また、「熱中症が心配なのに、頑なにエアコンをつけようとしない」「一人暮らしの父が物を足に落として骨折した」など、本人の意思や生活習慣に起因する問題も報告されており、離れて暮らしていると状況の把握や説得はより一層困難になります。
不安と向き合う家族の「支援」と「工夫」

親への支援は、子の「訪問」という物理的な努力に大きく依存しており、テクノロジーの活用などの選択肢はまだ十分に浸透していないのが現状です。まず、何らかの支援をしていると回答したうち「定期的な訪問」(56.8%)や「金銭的な援助・買い物の代行など」(55.0%)が半数を超えました。
一方で、「見守りカメラやセンサーなど」の機器やサービスの利用は、支援者の中でもわずか5.4%に留まっています。子の負担を減らし、どうしても生まれる「支援の空白時間」を埋めるためには、これまでのやり方を見直し、新しい支援の形を模索することが求められます。
「親の意思を尊重したい」からこそ生まれる課題
多くの人が支援に踏み切れなかったり、子の頑張りに依存しがちだったりする背景に目を向けると、「親の意思を尊重したい」という子の思いが、かえって具体的な行動をためらわせる一因になっている可能性がデータから見えてきました。

親とコミュニケーションを取る際、大切にしていることとして、「本人の意思を尊重する」が32.3%と最多だった一方で、「特に何も意識していない」も32.0%とほぼ同率でした。この結果は、多くの人が「親の意思を尊重したい」という気持ちは持ちつつも、「具体的にどう尊重すれば良いか分からない」「どこまで踏み込んで良いか迷っている」という複雑な心境の表れと推察できます。
親は「子どもに迷惑をかけたくない」、子は「親の自由を尊重したい」。この互いを思いやるがゆえの“配慮のすれ違い”が、結果的に重要な対話を先送りにし、互いに孤独感をもたらしてしまうという、遠距離介護特有の構造を生み出しているといえます。
不安解消の鍵は、空白時間を埋めるカジュアルな見守り

見守りサービスに対する、理想と現実のギャップも浮き彫りになりました。現在、親の支援をしている人の中で見守り機器を「利用している」のはわずか5.4%ですが、将来の備えとして「見守り機器を導入したい」と考えている人は、全体の13.7%にのぼります。
この約8ポイントの差は、「一定の必要性は感じるが、導入にはハードルがある」と考えている人が多いことを示唆しています。そのハードルとは、「監視されているようで親が嫌がるのでは?」「機械の操作が難しそう」といった、心理的・技術的な壁であると考えられます。
ポイントとなるのは常に監視するのではなく、安心感を共有するための「カジュアルな見守り」です。生活音や家電の使用状況など、プライバシーに配慮された情報からさりげなく安否を確認するサービスは、ネガティブなイメージを払拭し、子の不安解消と親のプライバシー確保を両立させる有効な選択肢となり得るでしょう。
「いつか」ではなく「今」始める。未来への備え
多くの人が親の将来への備えの必要性を感じつつも、3人に1人は具体的な準備に着手できていないという事実にも目を向ける必要があります。親の将来のために準備したいことを尋ねたところ、最多の回答は「将来のことについて、親子や兄弟姉妹で話し合う」(35.7%)でした。それに次ぐ回答が、33.0%を占める「特にない」です。
これは、備えの重要性を認識しながらも、何から手をつければ良いか分からず、行動を先送りにしている人の多さを物語っています。介護は、ある日突然必要になる可能性があります。漠然とした不安を具体的な行動に変え、「親が元気な今だからこそ話せる」という視点で未来に向けた対話を始めることが、何よりも重要です。
いざという時に慌てないための情報収集が重視されている
将来への備えとして、「情報収集」の重要性を認識している方も多く、特に公的な制度や専門機関に関する情報が重視されています。
将来の備えとして、「制度・サービスの情報収集」をしたいと答えた人は17.0%、「専門機関への相談」をしたい人は8.3%でした。合計すると、約4人に1人が、家族だけでなく外部の専門的な知見を頼ることを視野に入れています。
一方で、いざ調べるとなると「どこから手をつければいいか分からない」という方も多いでしょう。まずは、お住まいの地域で介護について広く相談ができる「地域包括支援センター」の存在を知っておくことが有効です。また、並行して「親の健康状態(持病、服薬状況)」「かかりつけ医」「緊急連絡先リスト」といった基礎情報を、家族内で共有しておくことが、万が一の事態に迅速かつ的確につながります。
遠距離介護における安心の第一歩は「対話」と「仲間づくり」
遠距離介護の不安を乗り越えるためには、やはり家族間のオープンな「対話」が不可欠です。「将来の話し合い」をしたいという人が35.7%と最も多いだけでなく、「兄弟・姉妹や親族との役割分担」が15.0%と、家族内コミュニケーションの重要性が広く認識されています。
話し合いを円滑に進めるためには、「親が望む暮らし」「家族内での役割分担(実務担当、金銭担当など)」「連絡のルール」など、具体的なテーマを事前に設定し、冷静に話し合う場を設けることが有効です。また、介護は一人で抱え込むと精神的な負担が大きくなりがちです。自治体やSNS上のコミュニティなどを活用し、同じ悩みを持つ「仲間」と繋がることは、有益な情報交換の場となるだけでなく、孤独感を和らげる大きな助けとなるでしょう。
親の意向を尊重しながら段階的な見守りサービスの導入がおすすめ
親子間のコミュニケーションに関する価値観や将来への備えについての考え方を踏まえると「親の意思を尊重しつつ、さりげなく見守りたい」というニーズを両立させるためには、見守りサービスを段階的に導入することが成功の秘訣です。
親の意思を尊重しながら、さりげなく日々の健康状態を把握するためには以下のような進め方が検討できるでしょう。

実際に見守りサービスを活用する際には、「通知は誰が受け取るか」などのルールを事前に家族で決めておくことが、プライバシーへの配慮とより安心できる運用の実現につながります。
まとめ
本記事の実態調査から、遠距離介護における最大の課題は、親の生活における「空白の時間」について、自立した生活を送りたい気持ちを尊重しながらいかに埋めていくかという点にあるといえます。物理的な距離はコミュニケーションの不足を生み、それが子の不安を増大させるだけでなく、親の体調の小さな変化を見逃すリスクに直結しています。
この課題に対し、親子間の対話の機会を増やすこと、公的サービスなどの情報収集を事前に行うこと、そしてテクノロジーを活用した「カジュアルな見守り」が有効な解決策となり得ます。遠距離介護の不安を、未来への安心に変えるため、その第一歩として、本記事で紹介したような「カジュアルな見守り」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。