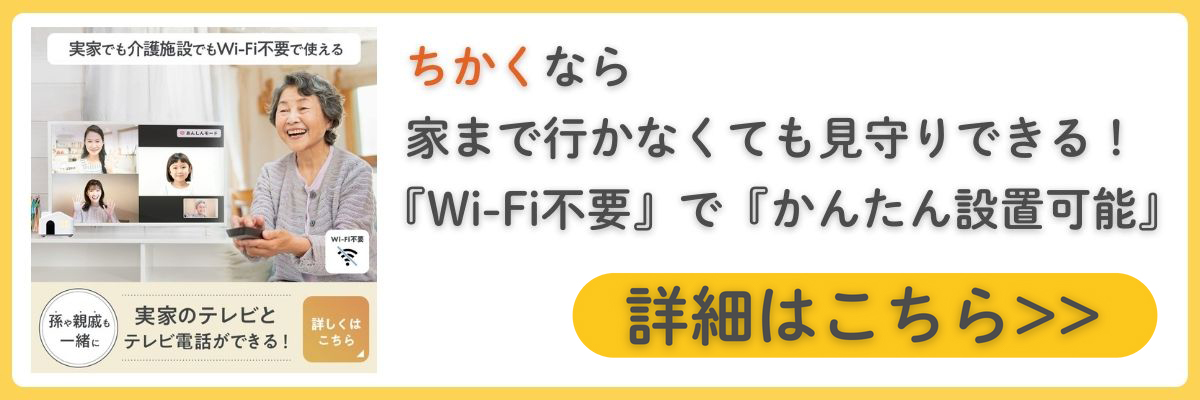一人暮らしの高齢者にとっての生きがいはどこにある?見つけ方も解説
コラム
一人暮らしの高齢者のうち、約6割の方が、友人や知人との交流や趣味の時間を通じて生きがいを感じながら日々を過ごしています。一方で、3人に1人程度は生きがいを感じられずに生活しているのが現状です。
本記事では、そうした状況を踏まえ、生きがいの見つけ方について解説します。
生きがいがある一人暮らしの高齢者の割合

内閣府の調査によると、一人暮らしの高齢者のうち、喜びや楽しみなどの生きがいを感じている人は、およそ6割程度とされています。生きがいの感じ方を度合いごとにわけると、下記のとおりです。
- 十分感じている……19.0%
- 多少感じている……40.5%
- あまり感じていない……28.3%
- 全く感じていない……4.9%
このことから、一人暮らしの高齢者の3人に1人程度は、生きがいを感じられずに生活しているといえるでしょう。
関連記事:高齢者の一人暮らしの現状は?起こり得る問題と安心のための対策
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
一人暮らしの高齢者が生きがいを重視すべき理由

一人暮らしで生きがいが少ない高齢者は、精神的・身体的な課題を抱える可能性が高くなりがちです。社会とのつながりが薄く、生きがいを感じられない状況が続くと、認知症リスクも高まるでしょう。
また、一人暮らしの高齢者には、下記のようなリスクも想定されます。
- 他者とかかわらないことで孤独感が高まり、うつ病を患ったり自殺するリスク
- 筋力や体力の低下により室内で転倒し、支援が必要になるリスク
- 他者とのつながりが希薄なため、孤立死しても誰にも気づかれないリスク
老後を生き生きと過ごすためには、さまざまな刺激を受けられる生きがいを見つけておくことが大切です。
関連記事:一人暮らしの60代が抱えやすい課題とは?暮らしのポイントや親の見守り方を解説
関連記事:高齢の親の一人暮らしの限界は?判断基準と生活を支援するサービスを解説
一人暮らしの高齢者が生きがいを感じる場面

高齢者が生きがいを感じる場面は、主に5つ挙げられます。
- 友人や知人と交流する時間
- 趣味やスポーツに取り組む時間
- おいしい食事を摂る時間
- テレビを見たりラジオを聞いている時間
- 家族団らんの時間
ここでは、内閣府の調査をもとに、一人暮らしの高齢者が生きがいを感じる具体的な場面を紹介します。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
友人や知人と交流する時間
生きがいを感じる場面として「友人や知人と食事、雑談しているとき」と答えた一人暮らしの高齢者は54.8%で、最も高い結果となっています。
特に女性の割合が高く、62.1%が生きがいを感じていると回答しました。この結果から、近所の人や長年の友人などとの社会的なつながりがあると、生きがいのある暮らしを実現しやすいといえるでしょう。
ただし、高齢者の友人や知人も、子世代との同居や施設への入居などで、交流の機会を維持できなくなる場合があります。そこで、友人や知人との交流だけに依存せず、他にも生きがいを見つけておくことが大切です。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
趣味やスポーツに取り組む時間
生きがいを感じる場面として、「趣味やスポーツに熱中しているとき」と答えた一人暮らしの高齢者は54.3%に上り、趣味の有無が老後の生活に大きく影響することがうかがえます。
ただし、下記のようなケースもあるため、老後に楽しみたい趣味やスポーツは複数用意しておきましょう。
- 細かい字を読むのが大変になり、昔のように読書を楽しめなくなった
- 模型制作をはじめたが、細かな作業が難しくなり、断念した
- 新たなスポーツに挑戦したが、ルールを覚えるのが大変で諦めた
視力や聴力など、いずれかの身体能力が低下しても生きがいを持てるよう、さまざまな趣味をもっておくとよいでしょう。また、継続して取り組めるように、ともに趣味やスポーツを楽しむ友人・知人を作っておくことも大切です。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
おいしい食事を摂る時間
「おいしいものを食べているとき」に生きがいを感じると答えた一人暮らしの高齢者は、51.6%に上ります。おいしいものを楽しめるような健康の維持が、老後の生きがいにもつながるといえるでしょう。
また、食事を摂るまでの調理過程では、素材や器具を揃えたり、献立を考えたり、ガス周りを安全に管理したりする認知能力が求められます。こうした行為は、認知症予防にも効果的と考えられるため、調理のできる健康状態であれば、自炊にも積極的に取り組みましょう。さらに、自宅での食事だけでなく、友人や知人と定期的に外食を楽しむことも、生きがいを感じる大切な機会になるでしょう。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
テレビを見たりラジオを聞いている時間
「テレビを見たり、ラジオを聞いているとき」に生きがいを感じると答えた一人暮らしの高齢者は47.9%でした。テレビやラジオは耳から情報を収集するため、日ごろから聴力チェックや補助器具の活用を意識しておくとよいでしょう。音が聞こえづらいと感じたときには、聴力検査を受けられる耳鼻咽喉科や補聴器専門店にまずは足を運んでみましょう。
また、テレビを快適に視聴するためには、定期的な視力検査や、場合によっては眼鏡の購入も必要です。映像や音声を存分に楽しめるよう、まずは眼科への受診を検討してみましょう。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
家族団らんの時間
一人暮らしをする高齢者が生きがいを感じる場面の第5位は「孫など家族との団らんのとき」で、36.1%に上ります。これに対し、配偶者と暮らす高齢者は58.6%、子の配偶者と暮らす高齢者は86.5%、孫と暮らす高齢者は84.2%と高く、一人暮らしの場合よりも家族団らんの時間が生きがいに直結していることがわかります。また、同居する家族がいないと、友人や知人がいたり、趣味があったりしても、寂しさを感じやすい傾向にあるともいえるでしょう。
さらに、子世代が働き盛りで忙しかったり、孫世代が成人して独立したりすると、会えるのは年に数回程度になり、寂しさが募りやすいことも指摘されています。生きがいを持ち続けるためには、日ごろから連絡を取り合える手段の確保が大切です。
関連記事:高齢者に寄り添うコミュニケーションの秘訣は?会話のコツも解説
関連記事:高齢者見守りサービスとは?6つの種類と選ぶポイントを解説
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
出典:山口県立大学学術情報「独居高齢者の生きがいに関する研究」
高齢者の生きがいに大切な「キョウイク」と「キョウヨウ」

高齢者が生きがいを感じるためのポイントとして、「キョウイク」と「キョウヨウ」があります。キョウイクは「今日、行く場所がある」ことを表すことばです。地域のなかに自身の居場所を見つけ、他者とのつながりや楽しみを見つけることが大切です。
一方、キョウヨウは「今日、用事がある」ことを示すことばです。たとえば、趣味や習いごと、ボランティアなどが該当します。用事がなければ外出もおっくうに感じやすいですが、用事があると外出する動機になり、他者とのかかわりも維持しやすくなります。孤立を防ぐためにも、一人きりの状態から徐々に行動範囲を広げていきましょう。また、自身が何に興味を持っているか、何が好きかを探り、生きがいになりそうな活動や居場所をはやくに見つけておきましょう。
新しい生きがいの見つけ方

老後に生きがいがない、あるいは少ないと感じる場合、どのようにして見つければよいか悩むかもしれません。その際は、高齢者の日常生活全般を支援する窓口である「地域包括支援センター」に相談してみるとよいでしょう。地域包括支援センターでは、地域で実施されている催しに参加できるほか、「生きがいがなくこの先が心配」といった悩みを、保健師をはじめとした専門家に相談できます。
仕事をはじめてみる
シルバー人材センターなど、高齢者向けの仕事に就くことを検討してみるのも一つの方法です。シルバー人材センターは、原則として市(区)町村単位で設置されており、入会を希望する場合は、自分の住む地域での登録方法をインターネットなどで確認できます。
仕事をはじめると仲間や顧客などとの交流が生まれ、他者に必要とされる実感を得やすくなるでしょう。実際に、内閣府による高齢者と生きがいに関する調査でも、生きがいを感じる場面として下記のような回答が寄せられています。
- 他人から感謝された時……35.2%
- 仕事に打ち込んでいる時……30.6%
- 収入があった時……26.5%
この結果からも、仕事をはじめることは生きがいを得られる有効な取り組みといえます。
出典:内閣府「令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(概要版)」
地域のコミュニティに参加してみる
地域で行われる催しや環境維持活動などのコミュニティに参加するのも有効です。参加を通じて思わぬ出会いから、食事や雑談を楽しめるような知人や友人といった関係性に発展する可能性もあります。新たな交流が生まれることで外出の機会が増えれば、結果として健康維持にもつながるでしょう。
地域のコミュニティを見つける方法としては、街の掲示板や市民だよりなどの広報誌を確認するほか、市役所などの行政へ問い合わせるのも有効です。
趣味や習いごとをはじめてみる
熱中できる趣味を見つけるために、習いごとをはじめてみるのもよい方法です。高齢者に人気のある趣味としては、次のようなものが挙げられます。
- パソコン
- 読書
- 映画鑑賞・DVD鑑賞
- 音楽鑑賞
- 散歩・ウオーキング
- 国内旅行
- 園芸(ガーデニング、盆栽、家庭菜園など)
- 写真撮影
こうした趣味を通じて友人や知人と出会う機会が増えると、さまざまな刺激を得られ、生きがいを感じられるでしょう。ただし、生きがいは円満なコミュニケーションがあってこそ得られるものです。コミュニティで良好な関係を築くためには、自身の価値観を押し付けたり、自慢話をしすぎたりしないよう注意しましょう。
介護サービスを利用してみる
介護サービスや介護施設では、レクリエーションとして催しが行われている場合があります。レクリエーションは基本的に任意参加のため、興味のあるものに参加してみるとよいでしょう。
内容は、お花見や旅行といったアウトドア系、カラオケやフラワーアレンジメントといったインドア系のようにさまざまで、両方を取り入れている施設もあります。レクリエーションへの参加により、入居者やスタッフとの交流が生まれ、孤独を感じにくくなるでしょう。
身体機能に不安がありサポートを求めている方や、予算に余裕のある方は、介護サービス・介護施設の利用を検討してみてもよいかもしれません。
家族団らんの時間をサポート|ちょうどよい見守りサービス「ちかく」

高齢者にとって、孫や子との交流は大きな楽しみの一つです。しかし、孫や子が忙しく、思うように会えずに寂しさを感じている方も多いかもしれません。そのようなときには、子世帯と親側の双方にとってちょうどよい距離感で利用できる見守りサービス「ちかく」を検討してみてください。
「ちかく」は、アプリを通じた見守りと、最大4画面までのテレビ通話ができるサービスです。一般的な見守りカメラのように常時映像を送信する仕組みではなく、アプリのアイコンを通じて見守りが行われる点が特徴です。さらに、テレビ通話を使えば、子や孫と実際に会っているような感覚で会話を楽しめるでしょう。ちかくのサービスについて、詳しくはこちらをご確認ください。
関連記事:ちかく|見守りよりも、やさしい選択。
まとめ: 生きがいを見つけて元気に過ごそう

一人暮らしの高齢者で、生きがいがある暮らしを送っている方は6割程度にとどまります。その多くは、友人や知人との時間や趣味の時間、おいしい食事などを生きがいにしていることがわかりました。
一方で、生きがいを持てない場合は、孤独感を抱いたり認知症の発症リスクが高まったりすることもあります。そのため、仕事探しやコミュニティ参加、専門家への相談などを通じて、まずは生きがいを探してみるとよいでしょう。
また、家族側は「ちかく」のようなサービスも活用し、一人暮らしの高齢者が無理なくあんしんして楽しく過ごせる工夫をしてみてください。
関連記事:ちかく|見守りよりも、やさしい選択。
※「ちかく」は株式会社チカクの登録商標です。