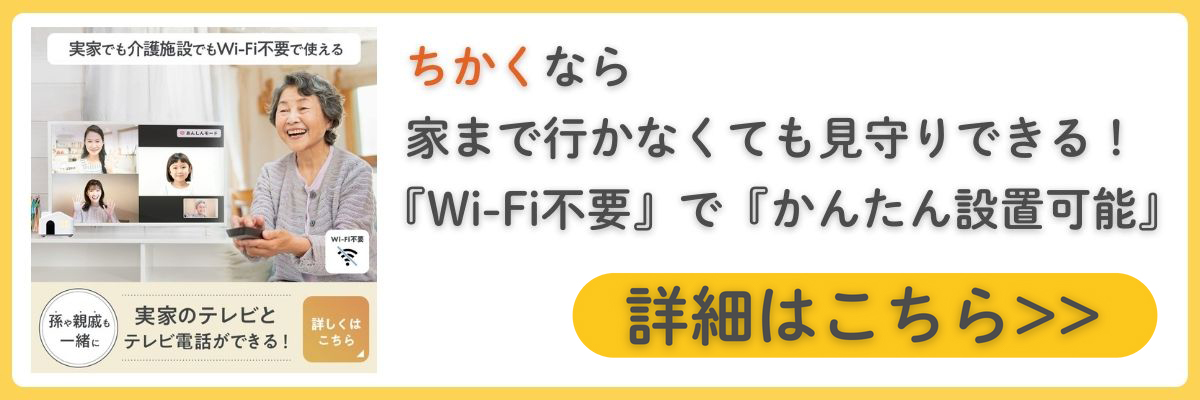一人暮らしの60代が抱えやすい課題とは?暮らしのポイントや親の見守り方を解説
コラム
60代で一人暮らしをしていると、「この先も健康に暮らしていけるだろうか」「生活費が足りなくなるのではないか」と、不安を感じることもあるでしょう。また、親と離れて暮らす方においても、「一人暮らしの親をどう見守ればよいのか」と、サポートのあり方に悩むこともあるかもしれません。
本記事では、一人暮らしをしている60代以上の方が抱えがちな不安を具体的に解説し、心身ともに健康に暮らしていくためのポイントや、親を見守る際に大切なポイントについてご紹介します。
一人暮らしの60代が抱える精神面の課題

60代で一人暮らしをしている方は、周囲の環境や今後の生活への不安から、精神的な課題を抱えているケースがあります。ここでは、内閣府が公表している「令和7年版高齢社会白書」のデータをもとに、60代の方が抱える課題を一つひとつ具体的に解説します。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
生きがいや楽しみを感じにくくなる
65歳以上の方が社会的な活動に参加していない場合、生きがいを感じにくくなることがわかっています。

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 3 学習・社会参加」
社会活動に参加している人と比べると、参加していない人では「生きがいを十分に感じている」人の割合が16.7%、「多少感じている」人の割合が6.3%低くなっています。個人で楽しむ取組みもよいですが、趣味・スポーツ・地域行事などで他者と関わった方が、生きがいや楽しみを得やすいといえるでしょう。
また、国立研究開発法人国立がん研究センターが実施した「多目的コホート研究」によると、趣味がない人よりもある人の方が認知症のリスクが18%低いことが明らかになっています。さらに、趣味が多い人ほど、認知症のリスクが低くなる傾向が見られました。
生きがいや楽しみが少なく、一人で家にいる時間が長い場合、認知症リスクにどのように対策していくかが課題となるでしょう。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 3 学習・社会参加」
出典:国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所予防関連プロジェクト「趣味と要介護認知症との関連について」
孤立死を意識するようになる

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 4 生活環境」
65歳以上を対象とした孤立死に関する意識調査では、「孤立死を身近に感じるか」という質問に対して「とても感じる」と答えた人が14.4%、「まあ感じる」と答えた人が34.3%で、合わせて48.7%にのぼりました。つまり、およそ半数の高齢者が孤立死を身近な問題と考えています。自ら外出し、他者と関わりを持つ外向的な方は孤独を感じにくいでしょう。一方で、内向的な方は自宅に引きこもりがちになり、他者との関わりや刺激を受ける回数が減少し、孤独感や認知症リスクを高める可能性も考えられます。

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 4 生活環境」
また、東京23区内では、一人暮らしをする65歳以上の人が孤立死するケースが増えています。上記の表からも、2013~2023年までの10年間において、孤立死の件数がおおむね増加傾向にあることがわかります。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 4 生活環境」
一人暮らしの60代が抱える金銭面の課題

一人暮らしの60代の方が抱える課題には、金銭的な問題も挙げられます。引き続き、内閣府が公表している「令和7年版高齢社会白書」のデータをもとに、詳しく解説していきます。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
年齢制限で働き先が見つからない
内閣府は、60歳以上で「今後仕事をしたい」と考えている人を対象に、現在収入を伴う仕事をしていない理由について調査を行いました。

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 1 就業の状況について」
その結果、最も多かったのは「健康上の理由」でしたが、次いで多かったのが「年齢制限で働くところが見つからないから」という回答でした。
また、60歳以上の人のうち「家計にゆとりがなく、多少心配である」「家計が苦しく、非常に心配である」と回答した人の割合は、以下のようになりました。
| 家計にゆとりがなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である | ||
|---|---|---|---|
| 60~64歳 | 男性 | 20.2% | 13.0% |
| 女性 | 25.8% | 8.4% | |
| 65~69歳 | 男性 | 22.7% | 10.5% |
| 女性 | 20.3% | 5.2% |
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」
この結果から、家計にゆとりがなく不安を抱えている人は、およそ3人に1人程度いることがわかります。
加えて同調査では、一人暮らしの人の収支状況についても調べています。以下のように、1か月あたりの収入では「10~15万円未満」と回答した人が最も多く、1か月あたりの生活費では「10~15万円未満」が最も多い結果になりました。一方で、収入の不足分は「節約などにより支出を減らす」と答えた人が最多でした。

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」

引用:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」
年齢が理由で働き口が見つかりにくく、収入を増やす方法が限られるなか、多くの人が家計に不安を覚えながらも節約などで対策をしていることが調査結果から見てとれます。節約などの対策をする際には「エアコンを使わない」「食事を抜く」など、極端な節約はせず、無理のない範囲で行うように心がける必要があります。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」
詐欺のターゲットになりやすい
60代以降になると、特殊詐欺やSNS型投資詐欺など、さまざまな詐欺のターゲットとして狙われるリスクが高まります。
2024年に認知された特殊詐欺の件数は、2万987件でした。そこから法人被害を除いた件数のうちの65.4%にあたる1万3,707件が、65歳以上の被害者です。預貯金詐欺では被害者の98.9%が65歳以上、SNS型投資詐欺では42.7%が60歳以上と被害が高齢者に集中しています。
これらの結果から、60代以降の方が詐欺に遭うことで老後の資金を失い「生活費が苦しくなる」「子や孫に迷惑をかける」というような可能性があります。家族間で日頃からコミュニケーションをとり、十分な対策を講じておく必要があるでしょう。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について 2 経済生活全般の状況について」
高齢の親が一人暮らしをするリスクについては、下記のコラムでも詳しく解説しています。
内部リンク:一人暮らしをしている親が心配!考えられるリスクや同居が難しい場合の対策は?
内部リンク:高齢者の一人暮らしの現状は?起こり得る問題と安心のための対策
一人暮らしの60代は健康面にも注意が必要

一人暮らしの60代の方が抱える問題はさまざまですが、特に健康面には十分な注意が必要です。健康寿命(日常生活に制限なく健康に生活できる期間)は男女ともに70代とされており、60代は健康の変化が起こりやすい時期ともいえます。
60代以降は要支援・要介護認定が増える
60代から70代にかけては、要支援・要介護の認定を受ける方が増える傾向があります。厚生労働省が実施した「介護給付費等実態統計」によると、年代別の要支援・要介護認定者数は以下のようになりました。
| 40~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1万4,900人 | 3万人 | 7万4,300人 | 16万6,600人 |
| 要支援2 | 2万5,400人 | 3万2,900人 | 7万5,000人 | 15万2,400人 |
| 要介護1 | 2万5,600人 | 3万6,700人 | 8万5,700人 | 18万7,700人 |
| 要介護2 | 3万5,300人 | 3万7,000人 | 7万9,600人 | 15万400人 |
| 要介護3 | 2万3,600人 | 2万5,500人 | 5万4,700人 | 10万5,600人 |
| 要介護4 | 2万1,700人 | 2万4,100人 | 5万2,700人 | 9万9,100人 |
| 要介護5 | 2万900人 | 2万600人 | 4万400人 | 7万2,700人 |
出典:政府統計の総合窓口(e‐Stat)「介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査) 19 認定者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級別」
表からもわかるように、60代後半から70代にかけて要支援・要介護認定を受ける人が増えはじめます。加えて高齢者の場合、「転倒・転落事故」「入浴中の事故」など家庭内事故をきっかけに寝たきりになるなど、生活に支援が必要になるケースも珍しくありません。
いつ生活支援が必要な状態になるかは予想できませんが、万が一に備えた対策が常に必要でしょう。高齢者に多い家庭内事故と対策については、下記のコラムで詳しく解説しています。
内部リンク:高齢者に多い家庭内事故とは?具体的な防止策や見守りの重要性
出典:政府統計の総合窓口(e‐Stat)「介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査) 19 認定者数,要介護(要支援)状態区分・性・年齢階級別」
介護や病気への支援が必要になる可能性が高まる
内閣府の調査によると、2022年時点の健康寿命は、男性で72.57年、女性で75.45年とされています。60代はこの健康寿命に近づく年代であり、健康上のリスクに備える必要性が高まる時期です。
特に一人暮らしの場合、何かがあってもすぐに気づいてくれる同居人がいません。そのため、いざというときに異変に気づいてもらい、助けを求められるような工夫が必要になります。
出典:内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版) 第2節 高齢期の暮らしの動向 2 健康・福祉」
一人暮らしの60代が生き生きと暮らすポイント

60代の方が不安なく、生き生きと過ごすためのポイントは、主に2つあります。1つ目は、運動を習慣化して体力の低下を防ぎ、健康寿命を延ばすことです。2つ目には、社会活動に参加して他者とコミュニケーションをとり、人とのつながりを持つことが挙げられます。
運動を習慣づける
年を重ねても生き生きと毎日を過ごすためには、運動習慣を維持することが大切です。短時間のウォーキングを習慣にしたり、ゴルフなど身体を動かす趣味や習い事をはじめたりするのもよいでしょう。
しかし急にハードな運動をすると、骨折などの怪我のリスクが高まります。そこで、友人・知人と誘い合わせて散歩をする、地域の催しに参加する、シニア向けのジムを利用するなど、ほかの人と協力しながら、無理のない範囲で少しずつ運動を習慣づけていくのが望ましいでしょう。
積極的なコミュニケーションを通じて人とのつながりを持つ
60代以降も元気に過ごすためには、積極的に人とコミュニケーションをとり、つながりを保つことが大切です。
たとえば、やりがいや楽しさを感じられるボランティア活動に参加するのもよいでしょう。あるいは、趣味や習い事を通じて、対人コミュニケーションの機会を増やすのもおすすめです。人との交流を通じてさまざまな刺激を受けることで、生き生きと毎日を過ごせる「自分の居場所」を見つけられます。
また、お子さまや親族と時折連絡をとることも大切です。こまめにやりとりができるよう、スマートフォンなどの通信機器の使い方を教わるのもよいでしょう。
60代で一人暮らしをする親を見守る方法

60代で一人暮らしをする親を見守るために、家族が取組める方法は主に3つあります。
1つ目は、定期的にコミュニケーションをとることです。こまめにコミュニケーションをとれば、親の孤独感を和らげます。2つ目は、地域やサービス事業者と連携して見守ることです。たとえお子さまが離れていたり、忙しかったりしても、周囲の人が異変に気づきやすくなります。3つ目は、お子さまが親の近くに住んでサポートすることです。近くにいれば、頻繁に親の様子を確認できます。
2週間に1回程度電話をする
定期的に会えない場合は、電話やビデオ通話で連絡をするだけでも、効果的な見守りになります。
内閣府の調査によれば、電話(ビデオ通話を含む)の頻度が高いほど、孤独感が軽減される傾向にあることがわかっています。

引用:内閣府孤独・孤立対策推進室「人々のつながりに関する基礎調査(令和6年) 調査報告書」
通話を全くしない場合と比べて、月に1回程度でも通話することで、孤独感の解消が期待できます。すでに取り上げたように、他者との関わりが希薄な場合は孤独感を抱き、認知症を発症するリスクが高まります。そこで、「週に1度、電話で会話する」「月に1度、家族全員がビデオ通話などで顔を見せ合う」などの習慣があるだけでも、孤独感が和らぐでしょう。そして、家族との電話により、万が一の変化にも早く気づけるでしょう。
出典:内閣府孤独・孤立対策推進室「人々のつながりに関する基礎調査(令和6年) 調査報告書」
内部リンク:高齢者に寄り添うコミュニケーションの秘訣は?会話のコツも解説
地域や事業者と連携する
仕事や家庭のことで忙しいと、定期的に連絡するのは難しいケースもあるかもしれません。その場合は、地域の支援や見守りサービスの事業者との連携も選択肢の一つです。たとえば、親が暮らしている地域で下記のようなサービスを利用できるか、あらかじめ確認しておくとあんしんでしょう。
- 訪問型見守りサービス
- センサー型見守りサービス
- 電話・メール型見守りサービス
- 緊急時通報型見守りサービス
もし怪我をしても、見守りサービスがあれば比較的早く異変に気づけるかもしれません。見守りサービスを導入することで、親子双方があんしんして暮らせるでしょう。
見守りサービスについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
内部リンク:高齢者見守りサービスとは?6つの種類と選ぶポイントを解説
内部リンク:親の安否確認の方法とは?サービスの種類や連絡がとれないときの対処法
近くのエリアに住む
お住まいのエリアを変えられる場合は、親の近くに住むという方法もあります。
「近居」は同居とは異なり、親とほどよい距離を保ちながら近くに住むスタイルです。それぞれが独立した生活を送りながらもコミュニケーションがとりやすく、必要なときにはすぐに助け合えるのが特徴です。様子を見に行きやすくなり「生活に必要な支出を削減していないか」「転倒して怪我をしていないか」などを確認しやすくなるでしょう。お互いのプライバシーや生活リズムを大切にしつつ、あんしんして見守れるでしょう。
ちょうどよい距離感の見守り「ちかく」

さまざまな見守り方法がありますが、「自分にとっても親にとっても、負担になるような見守りは避けたい」と思う方も多いかもしれません。そのようなときに、便利なのが、ドコモの見守りサービス「ちかく」です。
「ちかく」は、まるで実際に会っているかのように、テレビを通してビデオ通話ができる見守りサービスです。表情を見ながら話せるため、親に何か異変があった場合もすぐに気づくことができ、病院への受診を勧めたり、必要な支援機関に連絡をとったりしやすくなるでしょう。
内部リンク:見守りカメラのメリットや注意点は?選ぶ際のポイントも解説
まとめ

一人暮らしの60代の方は、精神面や金銭面、健康面など、さまざまな不安を感じやすい傾向があります。特に健康面では、要支援・要介護認定が増えはじめる時期であり、健康寿命も近づいてくるため、注意が必要です。
60代になっても健康的に生き生きと過ごすためには、ウォーキングなどの運動を習慣にしたり、コミュニケーションの機会を持ったりと、積極的な行動が必要です。子世代からのアクションも大切で、定期的な連絡や地域・事業者との連携、近居などが効果的な選択肢となります。
また、「ちかく」のように無理のない距離感で見守れるサービスの利用もおすすめです。互いにあんしんして暮らせるよう、あらかじめ準備を進めておきましょう。
詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。
ちかく|見守りよりも、やさしい選択